
お知らせ
「木と漆 3人展」2026年1月28日(水)~2月2日(月)
を開催予定です
銀座4丁目の「ギャラリーおかりや」での展示会です。
なかなか東京で展示会を行う機会がないのですが、ありがたいことに
2024年に続き、今年も展示をさせていただくことになりました。
うつわが中心ですが、新しいものもたくさん準備しました。
見にきてくださると嬉しいです。
※Instagramでも作品を少しずつ紹介していきますので、ぜひご覧ください。
HPのいちばん下にリンクがございます。
日時:2026年1月28日(水) ~ 2月2日(月)
11:00 ~ 19:00 (最終日は16:00まで)
場所:ギャラリーおかりや
東京都中央区銀座4-3-5 銀座AHビル B2F
℡03‐3535‐5321
※会期中は全日在廊いたします。(時間帯はまちまちになりますが、随時Instagramでお知らせします)
ご質問などがありましたら、こちらの問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

もくのすけ
「ふだん使いできるもの、役に立つもの、永く使えるもの」
をテーマに小さな工房でひとつひとつ制作しています。
もくのすけの工房ではうつわの主な材料であるケヤキ材を生木で仕入れて
乾燥させ木地挽き、漆塗りまでのほぼ全ての工程を行います。


兵庫県出身
京都伝統工芸専門学校木工芸科卒業
2007年より小田原漆器の伝統工芸士に師事し、木工ろくろ技術を学ぶ
2016年 小田原市箱根板橋に工房をかまえ、独立
小田原漆器
小田原漆器のこと
「伝統的工芸品」として経済産業大臣の指定を受けている小田原漆器。
起源は、室町時代の中期に箱根山中で入手できる木材を利用して木地挽きされた
挽物細工に漆を塗ったのがはじまりといわれています。
江戸時代に入ると、椀・盆・皿などの生産が盛んになり、相模漆の産出とともに、
他産地から塗師を招いて漆塗技法の向上が図られました。
これにより小田原漆器の特徴である、木地の木目を生かしたすり漆の技法や木地呂塗が発達し、
今日に至っています。
小田原漆器はふだん使いできる素朴な風合いの漆器です。


漆のこと
漆はウルシの樹から採取される天然樹脂塗料です。
もくのすけのうつわのほとんどは漆を塗って仕上げています。
漆を塗ることで水に強い丈夫なうつわになります。
漆はとても高価で、完成するまでにいくつもの工程があり手間もかかりますが、
自然の素材である木材には自然の樹から採れる漆がいちばん相性がいいと信じています。
お椀ができるまで

①木の仕入れ
切られて間もない木なので、まだまだ水をたくさん含んでいます。

④仕上げ挽き
鉋で削り、仕上げバイトで木肌をととのえ、木地は完成です。
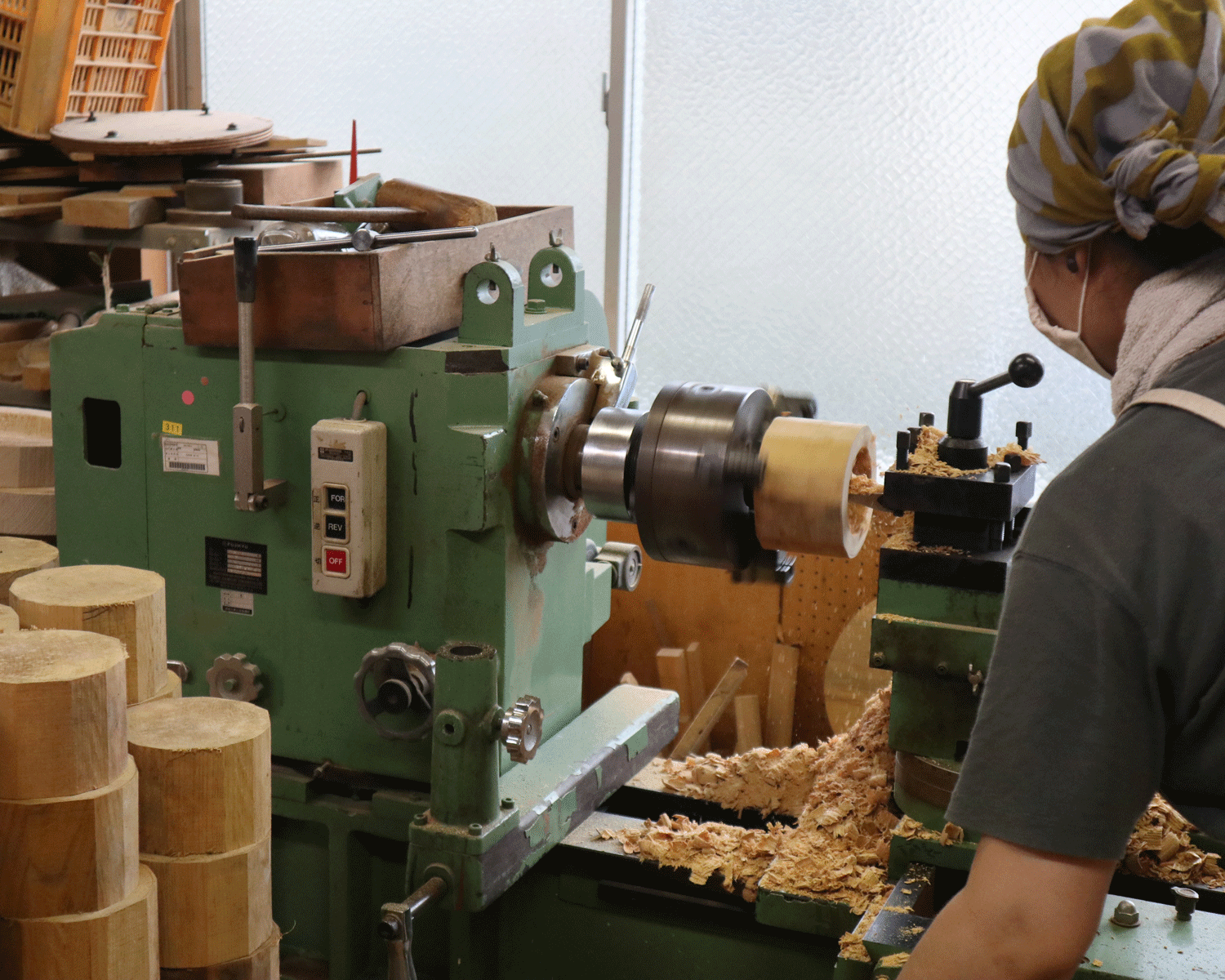
②荒挽き
早く乾燥するよう、仕上がり寸法から15㎜ほど余分に残し、ざっくりとしたお椀の形に削り出します。

⑤漆塗り
木地固め、すりさび、研ぎ、生漆塗り等の工程を繰り返し行い、丈夫なお椀が完成します。

③乾燥
水分が抜けやすいよう、すき間を開けて積みます。

*道具作り
木を削る刃物はすべて職人が鍛冶を行い作ります。
そして木を固定する木型等の治具もすべて自作します。




